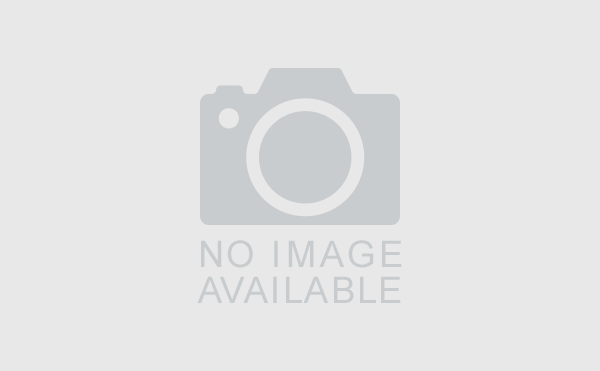【会長出張報告】(自費)
9月1日、松本市立博物館の『地獄の入り口 ―十王のいるところ―』展見学・窪田雅之前館長にお会いしました。
松本市立博物館の『地獄の入り口 ―十王のいるところ―』展(九月一日迄)、川野・桑久保紀代子氏(本会広報担当常任理事)・小林光考先生(明治大学商学部非常勤講師)とともに見学に行きました。前館長の窪田雅之先生(本会理事・松本市文書館・信州大学等大学非常勤講師)をお訪ねしました。
十王展は松本市内の各地の十王堂や私蔵の十王像があり、学芸員さん渾身の展覧会です。ちょうど会誌『日本の石仏』一八六号で「十王・十三仏」特集をしたところでしたので、最終日なんとか間に合って良かったです。 長野県には木造・石造等ユニークな十王群があり、その一端を覗うことができました。個人的には、奈川の古宿町会蔵の受審する亡者像など、他県ではなかなか見られない像や、どれも異なり、どれも互いに似ていない個性豊かな奪衣婆像など、興味深く拝見しました。 窪田前館長からは、『松本の道祖神』(松本市教育文化振興財団、1993年)をご恵贈頂きました(松本市教育委員会文化課文化係編で、二章四節を窪田先生ご執筆)。 また常設展では、旧城下町特有の木像道祖神などの展示があり、貴重な民俗資料の数々を見学しました。こちらは窪田先生が詳細に調査されています。



お蕎麦をお昼に頂いたあと、郷土玩具がお好きな小林光考先生のご希望で、松本押絵雛を継承するベラミ人形展の三村隆彦氏(66)を訪ね、ご両親から継承した押絵雛について、ご熱心なご解説を頂きました。厄払いの七夕人形など、松本独自のかたちと民俗に基づくこれらの人形を興味深く拝見しました。 窪田先生は、今年四月の石仏談話室での石仏入門講座で、道祖神についてお話頂きました。そこで市内の県一丁目の道祖神まで見学に連れて行って頂きました。背面に道祖神を他所に持って行くのならば、金十五両申し受けると書き(「天保十二辛丑正月日」〈1841年か、或いは正月日なので、1840年末〉(裏)「擔此神移他邑祭之為後栄祝賀之方金十五両受唯」)、「道祖神盗み」の民俗に関連する文言を実見することができました。
末筆ながら、窪田先生のいつもながらのお優しいご丁寧なおもてなしに心より感謝致します。